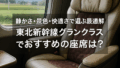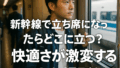新幹線フリーWi-Fiが繋がらない原因とは
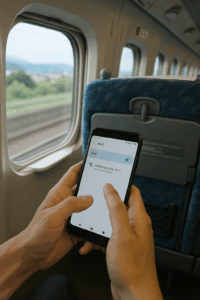
接続人数の多さ
まず真っ先に挙げられるのが、利用者の多さによる混雑です。
新幹線のフリーWi-Fiは、誰でも無料で使えるサービスのため、特に通勤時間帯や旅行シーズンには一気に利用者が増えます。
そうなると、回線がパンク状態になってしまい、まったく繋がらなかったり、繋がっても全然データがやり取りできない…なんてことがよくあるんですよね。
たとえば、ゴールデンウィーク中の新幹線で「メールすら送れない」と感じたことがある人も多いはず。
これはもうWi-Fiというより、まるで「通信制限を食らったスマホ」状態です。
誰かが重い動画やファイルをやり取りしていると、他の人はまともにネットが使えなくなるのも当たり前。
つまり、混雑時には「繋がらないのが普通」と割り切っておくのが現実的ですね。
トンネルや山間部の影響
新幹線って、意外とトンネルや山の中を通ることが多いですよね。
このとき何が起こるかというと、基地局との通信が途切れるんです。
そもそも新幹線のフリーWi-Fiは、車両と地上に設置されたモバイル回線の基地局との間で通信を行う仕組み。
だから、トンネルや山の中だと電波が入らなくなって、いきなり「切断」されたり、「接続中…」のまま進まなかったりすることがあるんです。
静岡〜名古屋間や、福島〜盛岡間など、長いトンネルが連続する区間では特に繋がりづらい印象です。
この点についてはもう、構造上の問題なので、ユーザー側でどうにかするのは難しいですね。
事前に「エリア的に不安定なんだ」と理解しておくだけでも、気持ちがラクになりますよ。
使用可能時間の制限
意外と知られていない落とし穴が、Wi-Fiの使用時間制限です。
新幹線のフリーWi-Fiには、実は1回の接続あたり「15分」という時間制限が設定されています。
そして1日に使える回数も限られていて、3回(=最大45分間)しか使えない仕組みなんですよね。
つまり、15分使って切れたあと、うっかり再接続せずに放置して「Wi-Fi繋がらない!」と焦る人も多いんです。
また、回数制限に達してしまったあとは、同じ端末ではその日はもう使えません。
「さっきまで使えたのに急に切れた!」という現象の裏には、この時間制限が潜んでいる可能性が高いですよ。
使用時間と接続回数をちゃんと把握しておくことが、快適なネット利用への第一歩です。
電波状況の弱さ
そもそも、新幹線内で提供されるWi-Fi電波って、そこまで強くないんですよね。
もともと電波は車内に設置されたルーターから飛ばされているんですが、車両ごとに違うアンテナ環境だったり、座る位置によって強弱があることもあります。
特に車両の端や、ドアの近くに座っていると、電波が弱くて繋がりにくいということがよくあります。
また、トンネルや高架の影響も受けやすく、そもそも車両が高速で移動しているので、電波が安定しづらいという宿命もあるんですよね。
Wi-Fiの電波って、止まってるカフェやオフィスでも弱いときがありますよね。
それを時速200km以上で走る環境で使うわけですから、ちょっとの不安定さは覚悟しておく必要があります。
機器との相性トラブル
最後に意外と見落とされがちなのが、使っているスマホやタブレットとの相性問題です。
特に古いOSを使っていたり、セキュリティ設定が強すぎると、接続認証ページが表示されなかったりします。
たとえば「Wi-Fiは繋がってるのにネットが使えない…」というケース。
これ、認証ページ(ログイン画面)が自動的に開かずに、接続できていないままというパターンが多いです。
AndroidならChrome、iPhoneならSafariを開いて、「http://www.google.com」などにアクセスすることでログイン画面が表示されることもあります。
また、VPNアプリやセキュリティソフトが原因で繋がらないこともあるので、一時的にオフにしてみるのも一つの方法ですよ。
新幹線フリーWi-Fiを繋げるための対処法5選

SSIDを手動で選ぶ
まず試してほしいのが、SSIDを自分で選択することです。
新幹線のWi-Fiは「Shinkansen_Free_Wi-Fi」という名前で提供されています。
でも、端末が自動で電波を拾ってくれない場合もあって、いつまでも接続待ち状態になってしまうんですよね。
そのときは、スマホやタブレットのWi-Fi設定を開いて、一覧の中から「Shinkansen_Free_Wi-Fi」を手動で選んでみてください。
自分で選択することで、接続がスムーズに進むことがあるんですよ。
特に複数のWi-Fiが飛んでいる駅などでは、間違ったSSIDを掴んでしまっている場合もあるので、必ず確認してみましょう。
手動で接続し直すだけで解決するケースも意外と多いです。
ブラウザでログインページを開く
Wi-Fiに繋がったのにネットが使えないとき、ログインページが開かれていない可能性が高いです。
実は、新幹線のフリーWi-Fiって、接続したあとに認証画面が表示されて「同意する」ボタンを押さないと、ネットには繋がらない仕組みなんです。
でも端末によっては、このログインページが自動的に開かないことがあるんですよね。
その場合は、自分でSafariやChromeを開いて、適当なサイト(たとえば「yahoo.co.jp」など)にアクセスしてみましょう。
そうすると強制的に認証画面にリダイレクトされることがあります。
それでも出てこない場合は、「http://www.google.com」や「http://example.com」など、軽いサイトにアクセスしてみてください。
無事にログイン画面が表示されたら、利用規約に同意してから通信がスタートします。
「繋がってるはずなのに使えない」ってときは、この方法で確認してみてくださいね。
再起動してリセット
何をしても繋がらない場合、端末を一度再起動するのも有効な方法です。
スマホやタブレットは長時間使っていると、通信情報やWi-Fi設定がうまく処理されなくなることがあります。
そんなときは再起動して、いったん接続設定をリセットしてみると、驚くほどあっさり繋がることも。
さらに、Wi-Fi設定から「Shinkansen_Free_Wi-Fi」を削除して、再度パスワードなしで接続し直すと、初期状態に戻せます。
この方法は特に、何度も乗車していて「前に接続した履歴」が残っているときに効果的です。
端末のクセが出やすい人ほど、再起動と接続履歴の削除で一発解決するケースも多いですよ。
迷ったら、とりあえず電源オフからの再チャレンジを試してみてください。
###④時間制限を把握する
意外と知られていない落とし穴として、利用時間の制限を把握しておくことも大切です。
前にも触れましたが、新幹線のWi-Fiは1回の接続で15分、1日で3回までという制限があります。
つまり、最大で45分間しか使えません。
たとえば、乗車してすぐに繋げて、しばらくSNSを見たり仕事のメールをやり取りしたら、それだけで時間切れになってしまうことも。
そんなとき、「何度やっても繋がらない…」と焦るのですが、じつは時間制限に引っかかっているだけということが多いです。
制限回数に達してしまった場合、同じ端末ではその日はもう接続できなくなるため、別のスマホやPCがあれば、そちらから再度接続を試してみましょう。
「時間切れ」のサインが出ないことも多いので、頭の片隅にこの仕様を入れておくと安心ですよ。
他の車両で再接続してみる
もし何をやっても繋がらないときは、車両を変えてみるのも効果的です。
実は、Wi-Fiの電波は車両ごとに発信されていて、場合によっては一部の車両だけ電波が弱い・不調ということもあるんです。
特に車端部(車両の前後)に座っていると、電波が不安定になりやすい傾向があります。
また、メンテナンスやトラブルで、特定の車両だけWi-Fiが無効になっていることもあるので、思い切って隣の車両に移動して再接続してみてください。
同じ列車内でも、電波状況が全然違うことがよくあるので、「この車両はダメだ」と感じたら移動する勇気も必要です。
ほんの一歩の移動で、ネット環境が激変することもあるんですよ。
それでも繋がらないときの代替手段4つ
テザリングを使う
どうしてもWi-Fiが繋がらないとき、一番手っ取り早い方法がスマホのテザリング機能を使うことです。
テザリングを使えば、スマホの4G/5G回線を使って、PCやタブレットなどの他の機器でもネットに繋ぐことができます。
最近のスマホであれば、設定画面の「インターネット共有」や「テザリング」メニューから簡単にONにできますよ。
ただし、これには注意点もあります。
スマホの契約プランによっては、テザリングにデータ上限がある場合もありますし、動画を見たりZoom会議をするような重い通信には向いていません。
また、山間部やトンネルではスマホの電波も不安定になることがあるので、全てが万能というわけではありません。
ですが、ちょっとしたメールの確認やブラウジングには十分対応できるので、いざというときに頼れる手段ではありますよ。
あらかじめ、モバイルデータ通信量やテザリングオプションの契約状況を確認しておくと安心ですね。
モバイルWi-Fiを準備
頻繁に新幹線を使うなら、モバイルWi-Fiルーターを持ち歩くのも選択肢の一つです。
特にビジネス用途でネット接続が欠かせない方にとっては、最も安定した通信環境が手に入る手段と言えます。
最近は大容量プランや5G対応の機種も出ていて、新幹線の移動中でも高速で安定した通信が期待できます。
たとえば、クラウドSIMタイプのモバイルWi-Fiであれば、乗車区間によって最適なキャリア回線を自動的に選んでくれるため、接続が切れにくいというメリットがあります。
月額契約だけでなく、旅行や出張のときだけレンタルするという使い方もできるので、状況に応じて選べるのもポイントですね。
初期費用はかかりますが、新幹線Wi-Fiの不安定さに毎回ストレスを感じているなら、真剣に導入を検討してみても損はないと思います。
駅のフリーWi-Fiを利用
新幹線の中で繋がらなくても、駅に着いたときにフリーWi-Fiを活用するという選択肢もあります。
主要駅では「JR-EAST_FREE_Wi-Fi」や「JR-CENTRAL_FREE」、「JR-WEST_FREE_Wi-Fi」といった各エリアのフリースポットが整備されていて、比較的快適に使えることが多いです。
特に停車時間が長めの駅(名古屋、京都、博多など)では、ドアが開いている間にサッと接続して、メールの送受信やクラウドへの同期を済ませる…といった使い方もできます。
また、新幹線を降りたあとでも、駅構内で仕事や連絡を済ませられるので、急ぎの作業がある人には助かりますよね。
ただし、セキュリティの面で注意も必要です。
公共のフリーWi-Fiは第三者に通信内容を盗み見されるリスクもあるため、できるだけVPNを使ったり、個人情報の入力は避けたりといった対策も忘れずに。
上手に活用すれば、Wi-Fi難民から一時的に脱出できますよ。
オフラインでもできる準備をする
最後に紹介したいのが、「そもそも繋がらないことを前提に準備しておく」という考え方です。
たとえば、仕事の資料やプレゼンデータ、動画教材などをあらかじめダウンロードしておけば、通信がなくても問題なく作業を進められます。
GoogleドキュメントやEvernoteなど、オフラインで編集できるツールも活用しておけば、新幹線の中でも生産性は落ちません。
また、Kindleなどの電子書籍を読んだり、Spotifyであらかじめダウンロードした音楽を聴いたりと、娯楽系も工夫しだいで通信不要にできます。
Wi-Fiに期待しすぎると、「使えなかったとき」のストレスが大きくなりがちです。
逆に、「繋がらなくても大丈夫」という状態を作っておけば、心にも余裕ができますよね。
通信環境が読めない場所でこそ、“オフライン前提の備え”が一番の安心材料になるというわけです。
そもそも新幹線フリーWi-Fiは使えるのか?リアルな評判まとめ
速度はかなり遅め
まず一番よく聞く声が、「速度が遅い」という評価です。
たしかに、SNSをちょっと見るくらいならまだしも、動画の視聴やデータのアップロードとなると、まったくと言っていいほど進まないことがあります。
実際、スピードテストで計測してみると、1Mbps未満しか出ないケースも珍しくありません。
これは、画像が多めのニュースサイトを読み込むのにも時間がかかるレベルなんですよね。
「これでWi-Fiって名乗っていいの…?」という声が出るのも、正直なところわかります。
LINEのメッセージすらタイムラグが発生することもあって、ストレスを感じる人も多いんです。
つまり、通信速度に期待してはいけない、というのが現実的な評価です。
安定性に欠ける
次に気になるのが、接続の安定性の低さです。
新幹線は高速で移動しているため、エリアによって通信環境が大きく変わるのは避けられません。
それに加えて、トンネルや山間部など、もともと電波が不安定な場所を通ることも多いので、「いきなり切れた」「何度も再接続になる」という現象がしょっちゅう起こります。
これが地味にストレスなんですよね。
何かを調べている途中にページが止まってしまったり、クラウドで作業していて「保存されてなかった…」なんてことも。
「繋がるけど、ずっと使えるわけじゃない」というのが、実際に利用した人たちのリアルな声です。
ビジネス利用など、安定した通信が必須の用途には向いていません。
動画視聴は基本的に厳しい
多くの人がやりがちなのが、「YouTubeでも見ながら移動しようかな」という使い方。
でも結論から言うと、新幹線のフリーWi-Fiで動画を観るのはほぼ不可能です。
たとえ画質を最低レベルに落としても、途中で止まる、再読み込みが頻発する、音声と映像がズレるなど、まともに楽しめる環境とは言えません。
これは通信速度の問題もありますが、帯域制限がかかっていて、一定以上のデータ通信が制御されているためです。
そもそも、動画はWi-Fi利用者の中でも特に負荷の大きい使い方なので、制限されるのは当然なんですよね。
移動中の暇つぶしに動画…という時代ではありますが、新幹線Wi-Fiに関しては期待しない方が身のためです。
ビジネス用途は厳しい
ノートパソコンを開いて、資料のチェックやオンラインミーティングをしたい…というビジネス利用も、正直難しいです。
特にクラウド上のデータを扱う作業や、ZoomなどのWeb会議ツールの使用は、通信が途中で切れるリスクが非常に高いため、実用的とは言えません。
たとえば資料を共有しながら打ち合わせする予定だったのに、途中で切れて相手と連絡が取れなくなった…ということも起こり得ます。
もちろん、簡単なテキスト送信やチャットなどは可能ですが、スムーズなやり取りを求める場面では明らかに不向きです。
出張の移動時間を活かしたい気持ちはわかりますが、「あくまで緊急用」と割り切って、オフラインでできる作業に集中する方が賢い選択です。
あくまで“緊急用”と考えるべき
ここまで見てきたように、新幹線のフリーWi-Fiは「使えるけど、実用的ではない」というのが正直なところです。
一応、無料で誰でも使えるという点ではありがたいのですが、そのぶん速度や安定性に制限があるのは仕方のない部分。
SNSを軽くチェックしたり、メールを一通送るくらいならなんとかなる…という程度で、頼りすぎると痛い目を見ます。
そのため、「何かあったときに最低限の通信ができればOK」と考えるのが正しい付き合い方。
動画視聴やビジネス利用はあらかじめ避け、オフライン活用や代替手段を併用する前提で使うのがベストです。
あくまでも、「あって損はないけど、メインの通信手段ではない」という位置づけで捉えておきましょう。