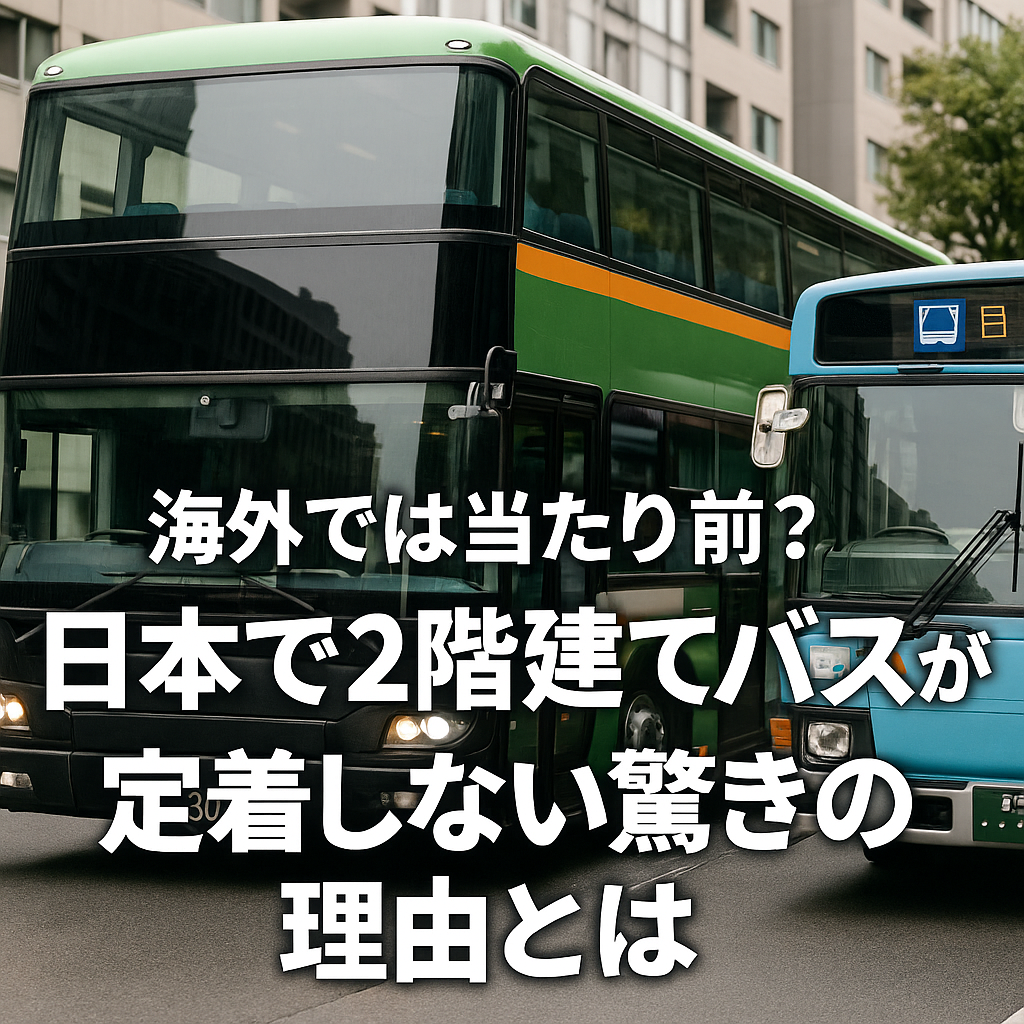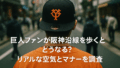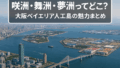「なぜ日本では2階建てバスがほとんど見られないの?」
旅行や海外ドラマで見かける2階建てバスに憧れを抱いたことがある方も多いのではないでしょうか?しかし、日本国内では、はとバスやJRの一部夜行バスを除いて、その姿を見ることはほとんどありません。
今回は、なぜ国際興業バスや京急バスのような大手路線バス会社が2階建てバスを導入しないのか、その裏にある事情や国内交通事情をわかりやすく解説します。
2階建てバスの特徴と世界での導入例
そもそも2階建てバスとは?
2階建てバスとは、その名の通り2層構造になっているバスのことです。車両の高さを活かして、同じ車体の長さでも多くの座席を確保できるのが最大の特徴です。海外ではイギリス・ロンドンの「ルートマスター」や、香港・シンガポールなどの都市で広く使われています。日本国内でも見かけることはありますが、その数は限られており、あくまで一部の観光・長距離路線に限られています。
その構造ゆえに、普通のバスよりも全高が高くなり、日本の狭い道路事情では走行できる範囲が限定されるという課題があります。また、乗客の乗降に時間がかかることや、2階部分の安全性・非常時の避難手順など、導入にはクリアすべきハードルが多いのも現実です。
2階建てバスは「大量輸送」を目的とする場面に向いており、都市の幹線路線や観光地での使用が適しています。逆に、街中の路線バスのように「短距離・頻繁に乗り降りがある」用途には向いていないといえます。
ロンドンや香港での導入背景
ロンドンや香港で2階建てバスが広く使われている理由は、都市の人口密度が非常に高く、公共交通機関に大量の人を効率的に運ばなければならないという事情があります。さらに、これらの都市では道幅やインフラが2階建てバスに対応するよう整備されており、車両の高さにも対応した信号や標識、橋梁などが一般的です。
ロンドンのバスは観光資源としての価値も高く、赤い2階建てバスはシンボルのひとつになっています。一方で香港では、鉄道網の補完としてバス路線が非常に発達しており、2階建てバスが主力車両として活躍しています。効率面と文化的価値の両方から、導入が自然に進んだといえます。
日本国内での採用事例(JRバス・はとバスなど)
日本でも2階建てバスは一部の用途で導入されています。代表的なのは「はとバス」の観光用バスや、「JRバス」の高速夜行バスです。はとバスのような観光用では、2階建てバスの高さから眺める景色が特別な体験となり、集客にもつながります。特に屋根がない「オープントップバス」は非日常感を演出し、インバウンド観光客にも人気です。
JRバスが運行する「ドリーム号」などの夜行高速バスでも2階建て車両が活躍しています。これは一人ひとりの座席に十分なスペースを確保しながら、定員を増やす目的で採用されています。運行距離が長く、停留所も限られている高速バスなら、乗降の手間も少なく、2階建て車両がうまく活かされているといえるでしょう。
2階建てバスの利点と課題
2階建てバスの最大の利点は「座席数の多さ」です。通常のバスに比べて、1台でより多くの人を運ぶことができ、運転手の人件費を抑えつつ輸送効率を高めることができます。また、眺望の良さや特別感もあり、観光バスでは高い評価を得ています。
一方で課題も多くあります。まず、高さによる制約で走行できる道路が限られること。また、重心が高くなるためカーブ時の安定性が悪くなりやすい点もあります。さらに2階への乗降には階段が必要で、高齢者や身体の不自由な方にとってバリアになることも多く、バリアフリーの面でもハードルが高いとされています。
どんな場面でメリットが発揮されるのか
2階建てバスが最大限に活躍できる場面は、「定員を増やしたいけど車体の長さを増やせない場合」や、「観光バスとして非日常を演出したい場合」です。高速道路を走る長距離夜行バスでは、途中の乗り降りも少なく、2階建てでも不便さを感じにくいです。
また、都市観光で景色を楽しむ目的なら、2階部分の高さは大きな魅力になります。ただし、日常の路線バスでは乗降が頻繁なうえに、信号や歩道橋、トンネルなどインフラとの相性も大きく影響します。このため、導入には「用途に応じた合理的判断」が不可欠といえるのです。
なぜ国際興業バスや京急バスは採用しないのか?
路線バスと観光バスの違い
2階建てバスの導入において、まず大きな分かれ目となるのが「どのタイプのバス運行か?」という点です。国際興業バスや京急バスは、主に日常的な交通インフラとしての「路線バス」を運行しています。一方で、はとバスや一部の高速バス会社は「観光用」や「長距離用」のバスを運行しており、性質が全く異なります。
路線バスは短い距離をこまめに走り、乗客の乗り降りが非常に頻繁です。このような運行スタイルでは、2階建てバスはかえって不便になる場合が多いです。乗降に時間がかかり、ダイヤに影響が出てしまうからです。また、路線バスではバリアフリー対応が求められており、段差や階段のある2階建て車両は不向きとされています。
車両コストとメンテナンスの問題
2階建てバスは車両の購入価格が高く、通常のバスに比べて1.5〜2倍ほどの費用がかかることがあります。国際興業バスや京急バスのような地域密着型のバス会社では、多数の車両を運行しているため、1台ごとのコストアップは経営に大きな影響を及ぼします。
さらに、車体構造が複雑になることで、整備や点検にかかる手間も増えます。部品や修理対応が特注になることもあり、ランニングコストが高くなる傾向にあります。路線バスでは「コスト効率」が非常に重視されるため、2階建てのような高額な車両は割に合わないという判断がされやすいのです。
道路インフラとの相性
2階建てバスを導入する際に最大の壁となるのが、日本の「道路インフラの制約」です。特に都市部では、歩道橋や信号機、標識、ガード下などの高さ制限が多く、2階建てバスが走行できるルートは限られています。京急バスの路線は住宅街を多く含み、道幅が狭かったり、交差点が複雑なエリアも多いため、高さだけでなく車体の取り回しも大きな課題となります。
また、国際興業バスも埼玉や東京の郊外エリアを中心に路線を展開しており、同様の問題を抱えています。こうした現実的な制約が、2階建て車両の採用を難しくしているのです。
安全面・バリアフリーの課題
国際興業バスや京急バスのような公共交通機関は、誰でも安心して利用できることが求められています。そのため、バリアフリー対応が非常に重要な要素となります。しかし、2階建てバスでは物理的に階段を使う必要があるため、車椅子やベビーカー、高齢者などには非常に不便です。
また、事故や火災、地震など非常時における避難経路の確保も課題です。狭い階段を通って2階から避難するのは非常に困難で、安全面の配慮としても一般的な路線バスに向かない設計と言えるでしょう。
乗降時間とダイヤ編成の問題点
2階建てバスは、構造上どうしても「乗降に時間がかかる」というデメリットがあります。特に通勤・通学時間帯には、限られた時間で多くの人が乗り降りをするため、このタイムロスは非常に大きな問題になります。
また、路線バスは定時運行が求められ、遅延が発生すると他の交通や利用者にも影響を与えてしまいます。2階部分の座席は魅力的かもしれませんが、毎回階段を上り下りすることは現実的ではなく、効率的な運行を阻害してしまう要因になるのです。
収益構造と運行目的から見る導入の可否
バス会社のビジネスモデルとは?
バス会社は一般的に「運賃収入」によって収益を得ています。特に路線バスの場合、毎日一定のルートを定期的に走り、乗車人数に応じた運賃を回収するのが基本的なビジネスモデルです。ただし、この運賃収入だけでは赤字になることも多く、国や自治体からの補助金や委託料でバランスを取っている会社もあります。
こうした背景から、車両のコストや維持費は経営に直結します。2階建てバスのような高額な車両を導入することは、利益率の低い地域交通事業においては非常に慎重に判断される必要があります。つまり、単に「座席が増えるから」といって採用できるほど簡単な話ではないのです。
収益を生むのは「何の路線」か?
2階建てバスが収益を生むためには、一定以上の「利用者数」と「運賃単価」が必要です。しかし、路線バスは1回の乗車料金が200~300円前後であり、長距離路線のような高額運賃にはなりにくいのが実情です。
これに対し、観光バスや高速バスは1人あたりの運賃単価が高く、長時間の乗車によって車両の効率も上がるため、2階建てバスの導入メリットが出てきます。逆に言えば、国際興業バスや京急バスのように地域の日常輸送を担っている企業では、2階建てバスは「コストに見合わない設備」になってしまうのです。
地方と都市部での戦略の違い
都市部の交通事業者と地方の交通事業者では、バス運行の考え方や必要とされるサービスが大きく異なります。都市部では交通量が多く、バスの定時運行や短時間での乗降が求められます。狭い道や交差点も多く、2階建てバスのような大型車両は運行しづらいです。
一方、地方では道路幅に余裕がある場合もありますが、乗客数が限られており、そもそも2階建てバスを満席にできるだけの需要が見込めないことが多いです。いずれにせよ、どちらのエリアでも「2階建てを導入する合理性」が見い出しにくいのが現状です。
座席数と運賃単価のジレンマ
たとえ2階建てバスで座席数を増やしても、運賃単価が上がらなければ利益は伸びません。逆に、利用者が定員に満たない状態で運行すれば、むしろ赤字が増えることになります。加えて、2階部分の座席は「利用率」が低くなりがちです。階段の上り下りを嫌がって1階に集中する乗客が多く、効率よく座席が使われないことも多いのです。
このように、座席数が多ければ多いほど良いという単純な理屈は、実際の運行現場では通用しません。特に短距離・低単価の路線バスでは「乗客の回転率」や「乗降のスムーズさ」が重視されるため、2階建て車両はかえって非効率になる可能性が高いのです。
「大型化=効率化」にならない理由
バスを大きくすれば効率が上がるという考え方は一見正しそうに見えますが、実際にはそう単純ではありません。大型車両になればなるほど、走れる道が限られ、運転にも高いスキルが求められます。また、事故時のリスクも増えるため、保険料やリスク対策にもコストがかかるようになります。
また、停留所の構造も関係してきます。現在のバス停の多くは通常の車両サイズに合わせて設計されているため、2階建てバスの長さや高さに対応できないこともあります。これらをすべて改善・整備するには多大なコストがかかり、結果として「費用対効果が合わない」という結論に至るケースが多いのです。
今後、日本で2階建てバスは増える可能性があるのか?
観光需要の回復とインバウンド効果
新型コロナウイルスの影響で大きく落ち込んだ観光業ですが、2024年以降はインバウンド(訪日外国人観光客)も着実に回復しています。これに伴い、観光客向けの交通手段として「2階建てバス」の需要が再び高まりつつあります。特に、東京・大阪・京都など観光地では「オープントップバス(屋根なし2階建て)」が人気を集めており、写真映えや非日常体験として多くの外国人観光客が利用しています。
このような背景から、今後は「観光向け2階建てバス」が都市部の特定ルートで増加する可能性があります。観光需要が集中するルートでは、1台あたりの収益も高く見込めるため、車両導入のハードルが下がるのです。
自動運転・EVバスの登場で変わる構造
交通業界全体では、次世代のバスとして「EV(電動)バス」や「自動運転バス」が注目されています。こうした技術の進化によって、今後はバスの設計自由度が大きく広がる可能性があります。例えば、バッテリー配置の工夫により車体の重心を下げたり、安全性を強化したりすることが可能になるかもしれません。
また、自動運転技術によって「ドライバー不足問題」が緩和されれば、少人数で多くの乗客を運べる2階建てバスの導入メリットも増します。これにより、これまで採算が合わなかったルートでも導入の可能性が出てくるでしょう。
バス業界の人手不足と運行効率化の流れ
バス業界では慢性的な運転手不足が問題となっています。特に地方では高齢化により人材確保が難しく、今後は「1人の運転手でより多くの乗客を運べる車両」が求められる流れになるでしょう。その点で2階建てバスは、運転手1人で通常の倍近い人数を運べるという意味で、一定のメリットがあります。
ただし、乗降に時間がかかることや、バリアフリー対応が難しい点は依然として課題です。今後、AI補助による乗降管理や、昇降機能付きの新構造など、技術的な革新が進めば、この課題をクリアできる可能性もあります。
地方自治体の導入支援や補助金の可能性
近年、地方創生の一環として「観光型公共交通」を支援する自治体が増えてきました。こうした施策の中で、観光振興や地域活性化を目的とした2階建てバスの導入が検討されるケースもあります。実際、補助金や助成金を活用して試験導入を行った自治体もあり、一定の成功を収めた例もあります。
このように、「観光+交通」の両面で地域に貢献できる施策として、2階建てバスは一部の地域では有効な選択肢となるかもしれません。ただし、定期路線として採算を取るには、やはり慎重な運用計画が必要です。
普及に向けた課題と期待される革新
2階建てバスの普及にはまだ多くの課題があります。たとえば、現在の道路インフラの制限、安全基準、バリアフリー対応、そして車両価格の高さなどです。これらをすべてクリアしない限り、全国的な普及は難しいのが現実です。
しかし、バス業界全体が大きな転換期にある今こそ、新しい形の2階建てバスが登場する可能性もあります。例えば、「軽量素材を使った低コスト車両」や「モジュール式の座席構成」など、これまでにないアイデアが現場に取り入れられることで、未来のバス輸送の在り方が変わるかもしれません。
2階建てバスが選ばれないのには「合理的な理由」がある
「使える場面」が限られている
2階建てバスは確かに視覚的なインパクトがあり、多くの人を一度に運べるという点で魅力的です。しかし、実際には「使える場面」が非常に限られています。観光バスや長距離高速バスのように、停留所が少なく、乗降の頻度が低いルートでこそ真価を発揮するのです。
一方で、通勤・通学に使われるような路線バスでは、短い間隔で乗り降りが発生するため、階段の上り下りが大きな負担となり、運行効率も悪化します。このように、2階建てバスは「万人向け」の交通手段ではなく、特定の条件が揃った環境下でのみ活用されるべき特殊な車両といえるのです。
現実的なコストと効率の判断
バス会社は「公共交通」を担う社会的使命を持ちながらも、企業としての採算性も重要な課題です。2階建てバスの導入には高額な初期投資が必要であり、さらにメンテナンスや保険、運転手の教育コストなど、多くの追加費用がかかります。
一方で、座席数の増加が必ずしも売上アップに直結するわけではなく、むしろ乗車率の低下や運行遅延による収益悪化のリスクもあります。このように、感覚的な「便利そう」「カッコいい」だけでなく、実際の運用コストと効率のバランスを見極めたうえで、2階建てバスが「選ばれない」という判断をしているのです。
今後の技術革新に期待
とはいえ、2階建てバスが完全に時代遅れというわけではありません。むしろ、観光需要やテクノロジーの進化によって、今後の活用範囲が広がる可能性は十分にあります。特に自動運転技術やEV車両の普及が進めば、これまでの課題だった乗務員コストや整備面の負担が大きく軽減されるかもしれません。
また、軽量化技術や新素材の導入、さらには昇降装置の進化によって、バリアフリーの問題も解決される日が来るかもしれません。こうした未来を見据えた技術革新が、2階建てバスの可能性を再び切り拓くカギになるでしょう。
消費者目線と事業者目線のギャップ
利用者の中には「2階建てバスに乗ってみたい」「もっと導入してほしい」という声もあります。確かに眺めも良く、特別感のある乗り物ですが、事業者側から見ればそれはあくまで「ニーズの一部」にすぎません。毎日運行を続けるには、効率性・安全性・コストすべてをクリアする必要があります。
このように、消費者が感じる「楽しさ」や「魅力」と、事業者が抱える「現実的な運行条件」には大きなギャップが存在します。2階建てバスが日常的に使われない理由は、まさにこの「現実と理想の乖離」にあるのです。
利用者にとって本当に必要か?
最後に考えるべきは、「2階建てバスは本当に日常生活に必要なのか?」という問いです。多くの人が望んでいるのは、定時運行され、座れる確率が高く、バリアフリーにも対応している「使いやすいバス」です。高さや構造の面白さは、日常の利便性とは別の話です。
つまり、2階建てバスは「話題性」や「特別な体験」としては有効でも、日常の公共交通には必ずしも必要とは言えないのです。そのため、現在のように限定的な用途で活躍しているという状況は、実は非常に合理的な結果だと言えるでしょう。
まとめ:国内バス運行事情から見る2階建てバスの立ち位置
2階建てバスが日本で広く普及していない理由は、単なる「コストの問題」ではありません。道路インフラ、乗降の利便性、安全面、運行効率、そして利用者ニーズなど、さまざまな要素を総合的に考慮した結果なのです。
もちろん、観光や夜行高速バスなど、条件が合えば今後も導入される可能性はあります。しかし、それはあくまで一部の用途に限定されるものであり、日常の路線バスとしての普及は難しいというのが現状です。
2階建てバスに対する興味や好奇心は今後も続くでしょう。その一方で、交通事業者は現実的かつ安全な選択をし続けており、それが私たちの暮らしの安心につながっています。