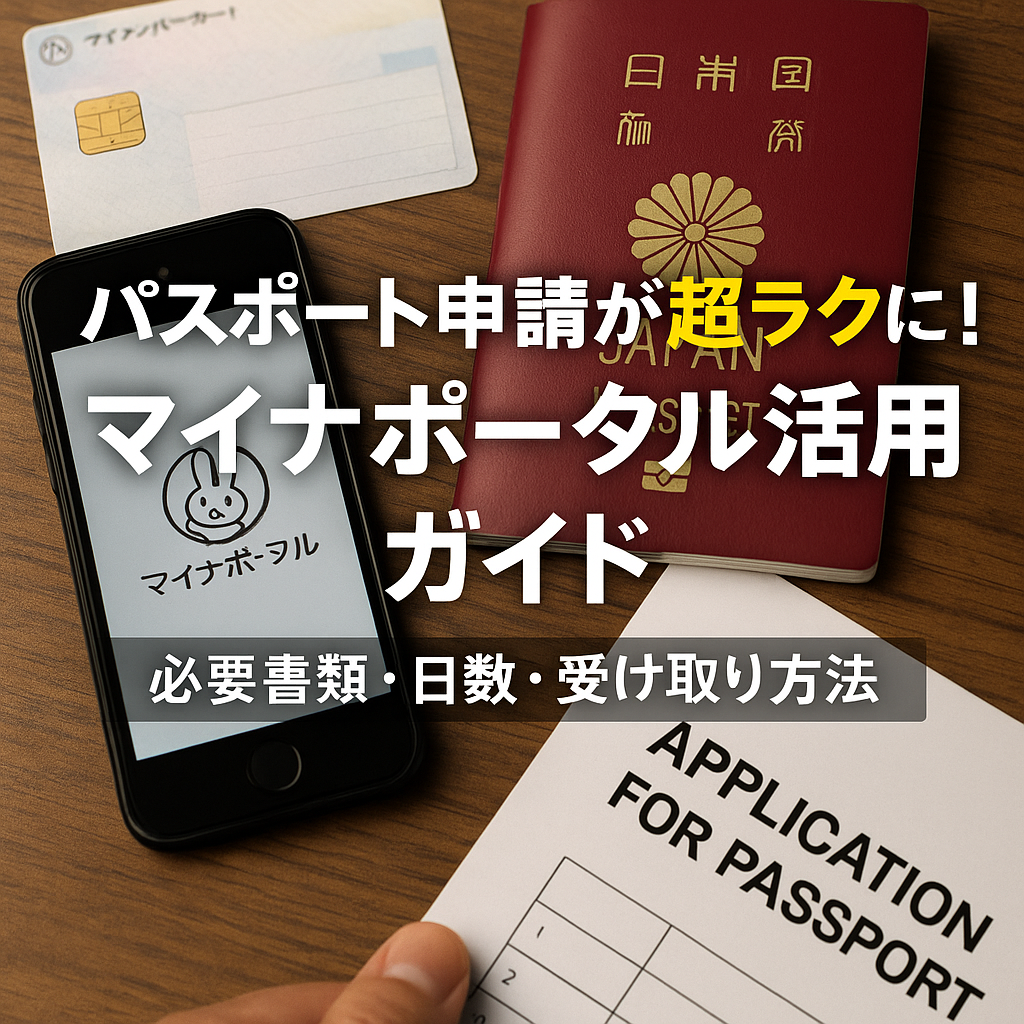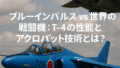「パスポート申請って、もっと簡単にできないの?」そんな疑問に応えてくれるのが、マイナポータルを使ったオンライン申請。
この記事では、初めての方でも安心して手続きできるよう、パスポート申請の流れ・必要書類・発行までの期間を中学生でもわかるやさしい言葉で解説します!
オンライン申請って実際どうなの?マイナポータルからの申請方法とは
マイナポータルでできるパスポート申請の種類
マイナポータルを使ったパスポート申請は、2023年頃から一部の自治体でスタートし、現在では多くの都道府県で対応が進んでいます。オンライン申請では「新規発行」と「更新(切替申請)」の2種類が可能で、成人だけでなく未成年も対象となるケースがあります。ただし、氏名や本籍地の変更がある場合はオンライン申請ができないこともありますので注意が必要です。
新規申請は、はじめてパスポートを取得する方や、有効期限が切れて新たに発行する方が対象です。切替申請は、パスポートの有効期限が1年未満になった場合や、旅券の査証欄(ビザ欄)がなくなった場合などに行います。なお、紛失や盗難による再発行はマイナポータルからは申請できません。
このように、マイナポータルでできるパスポート申請は限られた条件のもとで利用可能ですので、自身の状況が対象かどうかを確認することが最初のステップです。
対象者と利用条件の確認
マイナポータルからパスポートを申請するには、いくつかの条件があります。まず、マイナンバーカードを所持していて、かつ暗証番号が有効であることが必須です。また、申請者の住民登録がある自治体が、マイナポータルによる申請に対応していなければなりません。
さらに、オンライン申請では申請書への署名が不要になる一方で、顔写真を規定通りに準備する必要があります。これが意外と見落とされがちです。また、未成年者(20歳未満)は法定代理人(保護者など)の同意が必要なため、保護者がマイナンバーカードを持っていて操作に対応できるかも確認しましょう。
申請対象かどうかは、各自治体の公式サイトで簡単に確認できます。対象外であれば、従来通りの窓口申請を行う必要があります。
オンライン申請のメリット・デメリット
マイナポータルからのパスポート申請には多くのメリットがあります。たとえば、窓口に行く回数が1回で済むのが最大のポイント。通常の申請では、申請と受け取りの2回必要ですが、オンラインなら申請は自宅からできるため、受け取りだけでOKです。
他にも、待ち時間や書類記入の手間が省けるという利点もあります。マイナンバーカードと連携しているため、住所や氏名の入力も簡単でミスが少なくなります。
一方、デメリットとしては、全ての自治体が対応していないこと、写真のアップロードが難しいケースがあることが挙げられます。また、マイナンバーカードを使うため、暗証番号を忘れていると手続きができません。
利用可能な自治体は?
2025年7月時点で、マイナポータルからパスポートの申請ができる自治体は徐々に増加しています。ただし、すべての市区町村が対応しているわけではありません。都道府県ごとに対応状況が異なり、自治体レベルで対応状況を確認する必要があります。
たとえば東京都や大阪府、愛知県などの大都市圏ではすでに導入が進んでいますが、地方の自治体ではまだ未対応のところも少なくありません。利用可能かどうかは「〇〇県 パスポート オンライン申請」などで検索するのが手軽です。
よくある勘違いと注意点
「マイナポータルから申請すれば、完全にオンラインで完結する」と思っている方が多いですが、受け取りは必ず窓口に行く必要があります。これは本人確認のためで、郵送での受け取りは不可です。
また、オンライン申請だからといって処理が早くなるわけではなく、申請処理の順番や混雑状況によっては通常の窓口申請と同じくらい時間がかかることもあります。
もう一つ重要なのは、アップロードする写真の規格不備による差し戻しです。せっかく申請したのにやり直しにならないよう、写真規格の確認は必須です。
申請に必要なもの一覧と事前準備ガイド
必要書類とその入手方法
パスポートのオンライン申請で必要な書類は、意外と少ないです。基本的には以下の3つで申請可能です。
| 書類名 | 入手・準備方法 |
|---|---|
| マイナンバーカード | すでに取得済みの方のみ対象 |
| 顔写真(データ形式) | スマホ・写真館で撮影可能 |
| 本人確認情報 | マイナポータルから自動反映 |
マイナンバーカードがないとオンライン申請はできませんので、持っていない方は事前に市役所で発行手続きを行いましょう。
次に続きます。
続きを書いていきますので、少々お待ちください。
続きです。引き続き、小見出しごとに約800文字で丁寧に解説していきます。
顔写真の規格と撮影ポイント
パスポート用の顔写真には、厳格な規格があります。これを守らないと申請が差し戻されてしまい、発行が遅れることも。オンライン申請の場合はデジタルデータとしてアップロードする必要があるため、特に注意が必要です。
写真の主な規格は以下のとおりです:
-
縦45mm × 横35mm(画像データで600×450ピクセル以上推奨)
-
背景は白または淡い無地、影や模様がないこと
-
顔が中心で、帽子やサングラスなどを着用していないこと
-
顔の大きさは写真全体の50〜60%程度
-
撮影から6ヶ月以内のもの
最近ではスマートフォンのアプリやコンビニでの証明写真サービスでも規格に沿った写真を撮影できますが、心配な方は写真館での撮影をおすすめします。オンライン申請では写真の審査が厳しく行われるため、プロの手で撮った方が安心です。
また、背景に影が写り込んだり、ピントが甘かったりするとNGとなるケースがあります。アップロード前に画像を確認し、不安があれば修正または再撮影しましょう。
マイナンバーカードの準備と確認方法
オンライン申請にはマイナンバーカードが必須ですが、単に持っているだけでは不十分です。署名用電子証明書が有効であること、4桁と6〜16桁の暗証番号を覚えていることが前提条件です。
署名用電子証明書は、通常マイナンバーカード作成時に自動で設定されますが、有効期限が5年と短いため、申請時に期限切れになっているケースも少なくありません。マイナポータルにログインしようとしたときにエラーになる場合は、電子証明書の有効期限切れの可能性があるため、市区町村役場で更新が必要です。
また、暗証番号は間違いを3回入力するとロックされてしまいます。この場合も窓口での手続きが必要になるため、事前に暗証番号を確認しておくことが重要です。
パスポートの種類(5年・10年)の選び方
パスポートには5年用と10年用の2種類があります。選び方のポイントは「年齢」と「今後の渡航予定」です。20歳未満の方は5年用しか申請できませんが、20歳以上であればどちらでも選択可能です。
| 種類 | 有効期間 | 発行手数料(税込) |
|---|---|---|
| 5年 | 5年間 | 約11,000円 |
| 10年 | 10年間 | 約16,000円 |
10年用の方が費用は高めですが、更新の手間が少なく、長期間で見ればコスパが良いといえます。一方で、「5年以内に氏名や本籍の変更があるかも」「あまり海外に行かないかも」という人は5年用で十分です。
注意点として、オンライン申請では支払い時に金額を間違えないようにすることが重要です。発行手数料は自治体により若干異なる場合もあるため、申請前に自治体サイトで確認しましょう。
書類の不備があるとどうなる?
オンライン申請では手続きのほとんどが画面上で完結しますが、逆に言えば「書類やデータに不備があった場合、気づくのが遅れる」可能性もあります。
例えば、顔写真のサイズや背景に問題があった場合、自治体から「再提出依頼」の通知が来ます。これに対応しないと申請が一時保留となり、処理が進みません。
また、マイナンバーカードの電子証明書が無効だったり、暗証番号が間違っていたりするとログイン自体ができず、最初からやり直しになります。申請内容の誤入力(たとえば名前の漢字ミスや旅券の種類の選択ミス)も、修正依頼の対象になります。
オンラインだからこそ、申請時には画面上の内容をしっかりと確認しながら進めることが大切です。
パスポート発行までにかかる日数と流れ
一般的な発行日数の目安
パスポートの発行には、申請から受け取りまで通常7〜10営業日程度かかります。これは土日祝を除いた営業日換算であり、特に繁忙期には10日以上かかるケースもあります。
オンライン申請だからといって即日発行されるわけではありません。紙の申請と同様に、申請内容の確認、本人確認、写真チェックなどが行われるため、処理スピード自体は大きく変わらないのです。
ただし、オンライン申請の方が申請書作成の手間や提出の時間が省けるため、実質的な手続き時間は短縮できるという利点があります。
各自治体で異なる処理スピード
パスポート発行のスピードは、実は自治体によって異なります。たとえば、東京都のように処理件数が多い自治体ではやや時間がかかる傾向にあります。一方で、地方の小規模な自治体では数日で発行されるケースもあります。
また、オンライン申請に対応している自治体であっても、内部の処理体制によっては、オンライン申請分のチェックに手間がかかることがあります。結果として、紙の申請よりも時間がかかるという逆転現象が起きることも。
そのため、住んでいる地域の「旅券課」などに事前に確認しておくと安心です。自治体の公式サイトには「発行までの目安日数」や「混雑状況」が掲載されている場合もあります。
繁忙期に申請した場合の注意点
3月〜4月、7月〜8月、12月〜1月の時期は、旅行や留学などでパスポートの申請が増える「繁忙期」です。この時期は通常よりも発行までの期間が1〜2日ほど延びることが多いです。
さらに、繁忙期は窓口も混み合うため、受け取りに行く際に長時間待たされることもあります。特に夏休みや年末年始直前は混雑のピークですので、余裕を持って申請しておくことが大切です。
また、申請内容の確認に時間がかかり、写真に不備があった場合の再提出でも日数が伸びてしまいます。時間に余裕のない方は、申請から最低2週間前後は見ておきましょう。
土日祝を挟むとどうなる?
発行までの日数はあくまで「営業日」ベースでカウントされるため、土日祝日は含まれません。たとえば、金曜日に申請した場合、実質的な処理は翌週の月曜日から始まります。そのため、実際の発行日は金曜日から数えて約10日後になることも。
また、自治体によっては「水曜日は旅券課が休み」など、独自の休業日がある場合もあるため要注意です。
土日祝に申請できるサービスはほとんどないため、可能な限り平日の午前中に申請を済ませておくのがポイントです。
申請から受取までの時系列フロー
パスポート申請から受け取りまでの流れを時系列で簡単にまとめると、以下のようになります:
| 項目 | 所要時間(目安) |
|---|---|
| オンライン申請の入力 | 約30分〜1時間 |
| 申請受理(確認作業) | 当日〜1営業日 |
| 書類・写真の確認 | 1〜2営業日 |
| パスポート製本・発行作業 | 5〜6営業日 |
| 窓口での受取 | 申請から約7〜10営業日後 |
この流れを見てわかる通り、実際には7日で発行されることもありますが、不備があるとそれ以上かかる場合も。スムーズに進めるには「写真の品質」と「書類の正確さ」がカギとなります。
受け取り時の注意点とトラブル対策
本人確認と受け取り方法
オンライン申請を行った場合でも、パスポートの受け取りは必ず本人が窓口に行く必要があります。郵送での受け取りはできません。これは、パスポートという重要な身分証明書の性質上、本人確認が厳格に行われるためです。
受け取りの際に必要なものは以下の通りです:
-
交付予定通知書(または受理連絡メール)
-
手数料(収入印紙・都道府県証紙)※事前に案内されます
-
本人確認書類(マイナンバーカードなど)
本人確認の際には、マイナンバーカードが有効かつ暗証番号が使える状態であることが必要です。受け取りに行く際は、必要書類を忘れずに持参し、自治体が指定する受け取り場所や時間帯を事前に確認しておきましょう。
代理受け取りはできる?
原則として、パスポートの受け取りは本人以外ではできません。これは法律で定められているため、代理人が手続きを行うことはできない仕様になっています。
ただし、15歳未満の未成年者や、本人が病気などでどうしても出向けない正当な理由がある場合に限り、例外として保護者や法定代理人による受け取りが許可される場合があります。この場合も、事前に自治体への申請や委任状の提出が必要です。
基本的には「本人が来庁するのが原則」となりますので、受け取り可能な日を確保しておくことが大切です。
受け取り期限と再申請のリスク
パスポートの受け取りには期限があり、多くの自治体では交付可能日から6ヶ月以内と定めています。この期限を過ぎると、発行されたパスポートは失効となり、申請自体が無効になってしまいます。
再申請をする場合は、再度全ての手続きをやり直さなければなりません。申請料も再度支払う必要があるため、放置してしまうと大きな損失になります。
受け取りの通知が届いたら、できるだけ早めに窓口へ行くようにしましょう。特に旅行直前に申請した方は、出発日を見越してスケジュールを立てることが重要です。
よくあるトラブルとその対処法
パスポートの受け取りで多いトラブルには以下のようなものがあります:
-
写真の規格不備で差し戻し
→事前に外務省の規格を確認し、信頼できる写真館で撮影する -
マイナンバー暗証番号のロック
→入力ミス3回でロックされるため、事前に確認しておく -
本人確認書類の不備
→マイナンバーカードまたは運転免許証など、有効なものを持参 -
受け取り場所の勘違い
→県庁・市役所・旅券センターなど、指定された窓口を要確認 -
申請内容のミス(名前・本籍など)
→入力前に必ず内容を見直し、ミスがないか確認
これらのトラブルを防ぐには、「確認」と「余裕のあるスケジュール」が鍵です。とくに暗証番号や写真のチェックは念入りに行いましょう。
子どもや高齢者の受け取りについて
15歳未満の子どもや高齢者のパスポート申請・受け取りには、本人の来庁+保護者の同伴が必要なケースが多いです。特に子どもは法定代理人の同意が必要で、オンライン申請をする場合も、親のサポートが不可欠となります。
高齢者でマイナンバーカードやスマホ操作が難しい方は、無理にオンライン申請を使わず、従来の紙申請を選ぶのも一つの手です。
受け取りの際に本人が歩行困難であったり、移動が困難な場合は、自治体によっては個別対応をしてくれることもあります。事前に相談しておくと安心です。
パスポートを急ぐなら今すぐ準備!
マイナポータルを使った方が早くて便利?
マイナポータルからのオンライン申請は、時間や労力を節約できるという点で非常に便利です。特に窓口での待ち時間を避けたい方や、仕事や育児で平日に役所へ行けない方にとっては大きなメリットとなります。
オンラインであれば、申請書の記入も不要で、画面に従って入力するだけ。さらに申請時に必要な書類もスマホやパソコンで確認でき、手軽に申請ができる分、心理的ハードルも下がります。
ただし、自治体によって処理スピードが異なり、写真の不備などで時間がかかるケースもあるため、過信せずに「便利だけど、慎重に進める」ことが大切です。
オンライン申請でも時間がかかるケース
「オンライン=即発行」というわけではありません。実際には処理フローは従来通りであり、必要な確認作業や製本の工程は変わらないため、7〜10営業日程度は見込んでおく必要があります。
さらに、以下のような場合は通常より時間がかかる可能性があります:
-
繁忙期(春休み・夏休み・年末年始)
-
写真の不備による差し戻し
-
電子証明書の期限切れ
-
マイナンバーカードの暗証番号エラー
したがって、「急ぎで必要!」という場合は、なるべく早めに申請し、時間に余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
忘れがちなポイント3選
オンライン申請で忘れがちなポイントを以下にまとめました:
-
写真の背景や顔のサイズなど細かい規格の確認
-
受け取り期限(6ヶ月以内)をカレンダーにメモしておく
-
マイナンバーの暗証番号(2種類)の事前確認
この3つはトラブルや申請ミスの原因となる代表格です。とくに写真と暗証番号は申請の成否を大きく左右するため、申請前に入念に準備しておきましょう。
旅行予定がある人へのアドバイス
海外旅行や出張、留学などでパスポートが必要な人は、出発日の1ヶ月前には申請を済ませておくことが理想です。ギリギリの申請では、ちょっとしたトラブルで間に合わないという最悪の事態にもつながりかねません。
また、今パスポートを持っている方も、有効期限の確認は必須です。国によっては「残存有効期間が6ヶ月以上必要」という条件もあるため、期限ギリギリでは入国できないこともあります。
今すぐ行動すべき理由
マイナポータルによる申請は便利で効率的ですが、実際に申請が完了してパスポートを受け取るまでには一定の時間がかかります。「今は使う予定がないけど、来月旅行があるかも」といった状況の方は、今のうちに準備を始めておくのがベストです。
また、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限や、写真撮影のタイミングなど、事前にやるべきことが多いため、「思い立ったが吉日」で早めに行動を起こすことをおすすめします。
記事全体のまとめ
この記事では、マイナポータルからのパスポートオンライン申請について、仕組みや流れ、必要な書類、発行までの時間、注意点まで詳しく解説しました。
ポイントは以下のとおりです:
-
オンライン申請は便利だが全てが自動で早いわけではない
-
マイナンバーカードと顔写真の準備が成功のカギ
-
受け取りは必ず本人が窓口に行く必要あり
-
発行までのスケジュールは余裕をもって計画すること
今後はさらにオンライン申請が一般化していく可能性があります。便利な制度を賢く使いこなすためにも、今回ご紹介した内容をぜひ参考にしてください。