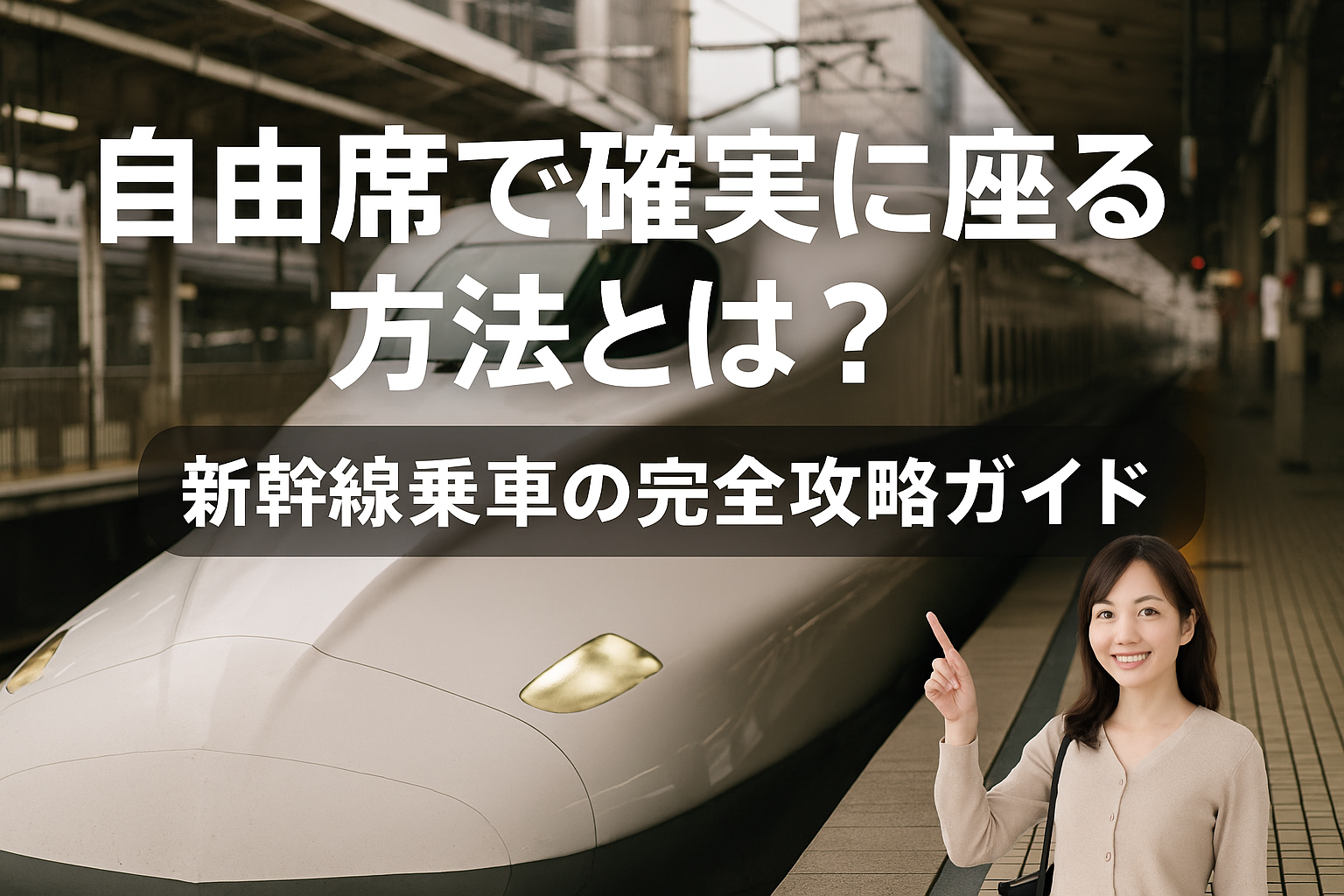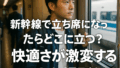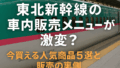新幹線の自由席、どうやって乗るか迷っていませんか?
「そもそもチケットはどう買うの?」「どこに並べばいいの?」「座れなかったらどうするの?」そんな不安、よ~くわかります!
この記事では、新幹線 自由席 乗り方を初心者さんにもわかりやすく、ステップごとに解説していきます。
混雑を避けるコツや、おすすめの時間帯、自由席のメリット・デメリットまでまるっとご紹介♪
これを読めば、自由席の乗りこなし方がスイスイわかるはずですよ~!
新幹線 自由席の乗り方を完全ガイド!

自由席のチケット購入方法
自由席に乗るための第一ステップは、もちろんチケットの購入から!
これは簡単で、駅にある券売機か、みどりの窓口で「自由席」を選んで買うだけなんです。
しかも最近では、スマホからも買えちゃう時代!「スマートEX」や「えきねっと」っていうサービスが便利ですよ。
スマホで事前にサクッと予約すれば、あとはピッとICカードをかざすだけで改札もスイスイ通れます。
初めてでも迷うことなくチケットが取れるので、気軽にチャレンジしてみてくださいね♪
自由席の並び方と場所
チケットを手に入れたら、次はいよいよホームへGO!
ホームには「〇号車 自由席」って書いてある表示があるので、そこに並んでください。
例えば、東海道新幹線なら1~3号車が自由席ってことが多いですね。
出発の15~20分前にはもう列ができてることがあるので、早めに並ぶのがおすすめです!
電光掲示板でも自由席の場所が表示されてるので、そちらもチェックしておくと安心ですよ~。
乗車から座るまでの流れ
さぁ、列車がやってきたら、いよいよ乗車タイム!
自由席は早い者勝ちなので、空いている席を見つけたらスッと座っちゃいましょう。
荷物は頭上の棚か、ひざの上に。周りの人にぶつからないように気をつけてくださいね。
満席で座れなかったときは、デッキで立っていてもOKです。
途中の駅で降りる人がいれば座れるチャンスもあるので、少し待ってみるのもアリですよ♪
混雑を避けるおすすめ時間帯
自由席って、時間帯によってめちゃくちゃ混むこともあるんですよね~。
たとえば朝の7〜9時や、夕方の17〜19時は通勤・帰宅ラッシュで激混みです。
逆におすすめなのは、10時〜12時くらいの午前中や、13時半〜15時半くらいの昼下がりタイム!
週末や祝日の前日、日曜の夕方も混雑しやすいので、日程に余裕がある人は避けるのがベターです。
「空いてる時間にゆったり移動♪」を狙うなら、時間帯選びがカギですよ~!
自由席と指定席の違いを徹底比較

料金とサービスの違い
まず気になるのが、お値段の差ですよね!
たとえば東京〜名古屋間だと、自由席の方がだいたい500〜700円くらい安くなるんです。
しかも、自由席は「予約なしで乗れる」っていう手軽さがウリ!
逆に指定席はちょっとお高めですが、そのぶん「確実に座れる安心感」がありますよ。
座りたい人には指定席、節約したい人には自由席が向いてますね♪
状況別のおすすめの選び方
「どんなときにどっちを選ぶか?」ってのも重要ポイント!
たとえば平日の昼間に1人でサクッと移動するなら、自由席で十分です。
でも、土日の朝や夕方、連休中とかは人が多くて座れないことも…。
家族旅行とか、小さい子どもが一緒のときは、指定席のほうが絶対にラクです!
予定がはっきりしているときは、あらかじめ指定席を予約しちゃうと安心ですよ~。
快適さ・安心感の違い
座席の広さやクッションはほとんど同じなんですが、気持ち的には結構差が出ます!
指定席は「絶対に座れる」っていう安心感があって、のんびりできますよね。
自由席は「空いてたらラッキー♪」な反面、乗る前からちょっとドキドキ…。
立ったままになる可能性もあるので、快適に過ごしたい人は指定席がおすすめかも。
その時々の気分や予定に合わせて、上手に選んでくださいね~!
初めての人が不安に思うことQ&A

スマホで自由席を買える?
はい、スマホでも自由席のチケットは買えちゃいます♪
JR東海の「スマートEX」や、JR東日本の「えきねっと」などの公式サービスを使えば、自宅でサクッと予約できますよ。
ICカードと連携すれば、発券も不要で改札をスーッと通れるんです!
アプリで空席確認もできるし、当日思い立ってもすぐ乗れちゃうのがうれしいポイントですね。
遅れても自由席に乗れる?
もし予定していた新幹線に間に合わなくても、心配いりませんよ~!
自由席のきっぷは、その日中なら他の列車にもそのまま乗れます。
だから「1本逃した…」というときでも、次の便の自由席に並べばOKなんです。
ただし、翌日以降に使うことはできないので、日付には要注意!
割引チケットやネット予約の場合はルールが異なることもあるので、事前に確認しておくと安心ですね。
座れなかったらどうする?
自由席が満席で座れなかったときは…ちょっぴり残念ですが、立ったまま乗車することもできます。
デッキや車両の端っこなど、安全なスペースでしばらく立っていれば、途中駅で席が空くこともありますよ♪
もし混雑がすごい場合は、次の列車を待って乗るという手もあります。
新幹線 自由席を上手に使う5つのコツ

狙うべき車両番号
自由席が設定されている車両は、新幹線によって違いますが、だいたい1~3号車が多いです。
その中でも、1号車や3号車の端っこは、案外空いてることがあるんですよ!
ホームには「◯号車 自由席」って書いてある表示があるので、事前にチェックしておくのがおすすめです。
電光掲示板で確認できる場合もあるので、乗る前にさっと目を通しておきましょう~。
並ぶベストなタイミング
良い席をゲットしたいなら、やっぱり「並ぶタイミング」が大事です!
出発の15〜20分前くらいにホームに行くと、ちょうど良いポジションを取れることが多いんですよ♪
特に始発駅では、列の先頭に並べれば確実に座れるチャンスがアップ!
時間に余裕を持って行動するのが、自由席成功のコツなんです。
荷物を少なくしておく
自由席では「身軽さ」が武器になります!
大きなスーツケースがあると、棚に乗せるのも大変だし、空席が見つかっても移動がもたついてしまうことも…。
なるべくコンパクトなリュックや肩掛けバッグなどにしておくと、スムーズに行動できますよ。
荷物が少ないと、周りの人にも気を使わずに済むので一石二鳥です♪
窓側席を確保するコツ
せっかくなら窓の外の景色を楽しみたい!って人も多いですよね。
コツはズバリ「ドアが開いた瞬間に、すぐ入る!」これだけです。
ドアから少し離れたところに並んでおくと、競争率が低くて狙い目です♪
中に入ったら、奥のほうまでスッと進んでみてください。意外と空いてたりしますよ~。
帰りは指定席も検討
行きは自由席で節約しても、帰りってけっこう疲れてるんですよね…。
だから「帰りは指定席」っていうのも、すごくアリだと思います!
連休の最終日や夕方の列車は混みやすいので、帰りだけでも席を確保しておくと安心です♪
スマホでパパっと変更できるので、移動中でもラクラクですよ~。
>どうしても座りたいときは、当日でも指定席に変更できるケースがあるので、駅員さんに相談してみてくださいね!
新幹線 自由席のメリットとデメリット
自由席のメリット
まずはなんといっても、料金が安い!これが自由席の最大の魅力です♪
指定席よりも数百円~1,000円くらいおトクに乗れるんですよ~。
そして、事前予約なしでもサクッと乗れるのもポイント!
予定が変わっても気にせずに乗れるので、「急に決まったお出かけ」や「ゆるっと旅したいとき」にぴったりです。
スマホでも気軽に購入できるので、思い立ったらすぐ行動できるのも嬉しいところですね。
自由席のデメリット
一方で、デメリットもちゃんと知っておきたいところ。
まず、混雑時は「座れないリスク」があるんです。
特に通勤ラッシュや連休中は長~い列ができてて、座れずに立ってる人も結構います…!
それに、複数人で乗るとバラバラに座る可能性が高いので、家族旅行やグループ移動のときはちょっと不便かも。
「確実に座って快適に移動したい!」という人には、指定席のほうが向いているかもしれませんね。
まとめ
今回は「新幹線 自由席の乗り方」について、初心者の方にもわかりやすく解説してきました。
チケットの買い方から、ホームでの並び方、座席の取り方や混雑を避けるタイミングまで、自由席の不安がスッキリ解消できたのではないでしょうか?
自由席は使い方さえ覚えれば、とっても便利でコスパも良い選択肢です。
旅のスタイルやタイミングにあわせて、上手に活用してみてくださいね♪
この記事が、あなたの快適な新幹線旅のお手伝いになればうれしいです!