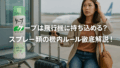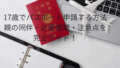長距離バスでの移動中、「通路側に座ったけど、マナーって何かあるのかな?」と感じたことはありませんか?
狭い空間での数時間、ちょっとした気配りや一言の声かけが、旅全体の快適さを大きく左右します。
本記事では、通路側に座ったときに気をつけたいマナーや、自然で感じのよい言葉のかけ方、実際の体験談まで、わかりやすくご紹介します。
読み終えるころには、あなたも“マナー上級者”になれるかも?
通路側の座席に座るときに押さえておきたい基本マナー
周囲の迷惑にならない座り方とは?
長距離バスでは限られた空間の中で多くの人が同じ空間を共有しています。そのため、通路側に座る人が気をつけるべき最初のマナーは「できるだけ他人のスペースを侵害しない」ことです。特に、隣の窓側に座る人が出入りする可能性があるため、自分の体や荷物が通路や隣席に入り込まないように注意が必要です。
通路側の人が足を広げて座っていたり、ひじを大きく張っていたりすると、隣の人が圧迫感を感じてしまいます。リクライニングを使うときも、後ろの人への配慮が欠かせません。席を倒す前には一言「少し倒してもいいですか?」と聞くのが基本です。
また、荷物の置き方にも気を配りましょう。通路にかばんを置いてしまうと、乗降の際に他人の邪魔になったり、つまずきの原因になったりします。リュックなどは膝の上や足元に置くのではなく、可能なら前の座席下など目立たない場所にしまうのが理想です。
一見些細なことでも、こうした気遣いが快適な旅につながります。自分の居心地だけでなく、周囲への影響を考えた行動を心がけましょう。
リクライニングの前にひと声かけるべき?
リクライニングシートは長距離移動を快適にするための機能ですが、それを使うときには周囲への配慮が必要です。特に、通路側に座っている人がリクライニングを倒す場合、自分の後ろにいる人のスペースを急に圧迫してしまうことがあります。
そんなとき、「少し席を倒してもいいですか?」と一言声をかけることで、相手の不快感を避けることができます。もし後ろに座っているのが子どもや高齢者の場合、急な動きは特に驚かれることがあるため、声かけはより重要になります。
また、リクライニングを倒すときの動作も大切です。勢いよく倒すのではなく、ゆっくりと静かに動かすことで、後ろの人への衝撃を最小限に抑えることができます。
マナーとは「相手を思いやる気持ちの表現」です。たった一言の声かけが、バス内の雰囲気を和らげ、気持ちよく過ごせる空間づくりにつながります。
足を通路に出すのはNG?
長距離バスでは通路のスペースも非常に限られています。とくに夜行バスや満席の便では、通路の狭さが気になることも多いでしょう。そんな中、通路側に座っている人が足を通路にはみ出すように出してしまうと、他の乗客が通るときに非常に邪魔になります。
実際に多くのトラブルや軽いケガの原因となっているのが「足のはみ出し」です。夜間など薄暗い車内では、足が出ていることに気づかずつまずいてしまう人もいます。また、通路を飲み物や荷物を持って移動している乗客や車内サービスのスタッフにとっても障害になってしまいます。
足を組むときも注意が必要です。片足を外側に出してしまうような組み方は避けましょう。どうしても足が疲れる場合は、膝を立てるなどして自分のスペース内で対処するのがマナーです。
快適さと安全を両立するためにも、通路をふさがないことを意識しましょう。
トイレのために通る人への配慮
通路側に座っていると、どうしても窓側の人がトイレなどで立ち上がるときに道をあけなければなりません。このとき、気まずい思いをさせたり、無言で圧をかけてしまったりすると、相手にとってストレスになります。
まず重要なのは、相手が立ち上がりたそうにしていたらすぐに気づく「気配りのセンサー」を働かせることです。スマホに夢中になっていたりイヤホンで周囲の音が聞こえなかったりすると、相手が困ってしまいます。
また、立ち上がる際は自分の荷物を一度よける、カーテンを開けるなどの動作もセットで行いましょう。そして「どうぞ」「すみません、ちょっと出ますね」といった言葉を交わすことで、スムーズで気持ちのよいコミュニケーションが取れます。
誰にとっても気まずくならない対応こそが、本当のマナーです。
乗降時のスマートな立ち方・どき方
乗降時には乗客全体が一斉に動くこともあるため、通路側に座っている人の動きが非常に大事になります。窓側の人が先に降りたいのに、通路側の人が立ち上がらない、荷物整理に手間取る、スマホをいじっていて気づかない……といったことがあると、車内全体の流れが滞ります。
スムーズにどくためには、到着直前のアナウンスやバスの停止に注意を払うことが重要です。自分の停留所でなくても、隣の人が降りそうなら「お降りになりますか?」と聞いてあげるとスマートです。
また、通路に一度しっかり出てから道をあけ、相手が出たら自分の荷物を再び持つ、という動作の順番もポイントです。狭い空間でも余裕を持った行動を意識すると、全体の流れがスムーズになり、他の乗客からの印象も良くなります。
小さな配慮の積み重ねが、マナー上級者への一歩です。
自然で感じのいい言葉かけの例集
「すみません、ちょっと通ります」など基本の声かけ
通路側に座っていると、隣の窓側の人がトイレや荷物の出し入れなどで移動したいときがあります。そんなとき、無言でどいてもらうのは相手にとって不安や戸惑いを与えることがあります。そこで大切なのが、自然で簡単な声かけです。
たとえば、「すみません、ちょっと通りますね」や「通していただけますか?」といった言葉は、非常にシンプルながら相手に安心感を与える効果があります。このような一言があるだけで、コミュニケーションがぐっとスムーズになります。
声の大きさも重要です。大きすぎる声は周囲の迷惑になりますし、小さすぎると聞こえないことも。相手の顔を見て、少し声を落として伝えると丁寧です。
そして、こうした声かけは義務ではなく「思いやり」です。バスという閉ざされた空間だからこそ、ほんの一言がその場の空気を穏やかにします。余裕を持って伝えることで、あなた自身の印象も良くなります。
相手が驚かないように配慮する言い方
バス内では多くの人が静かに過ごしており、とくに夜行バスでは睡眠中の人もいます。そんな中で急に声をかけたり、体を触って起こすような行動は避けたいものです。相手が驚かないようにするには、まず「視線を合わせる」「近すぎず遠すぎずの距離で話す」ことがポイントです。
例えば、肩を軽くたたいて驚かせるのではなく、少し距離をとった状態で「お休みのところすみません、通らせていただけますか?」といった丁寧な表現が効果的です。優しく落ち着いたトーンで話すことで、相手も落ち着いて対応できます。
また、突然の動作や声かけは避け、相手が気づいてから声をかけるようにするとベターです。目が合ったときに軽く会釈をするだけでも、十分に気持ちが伝わります。
相手をびっくりさせないことはマナーの一環です。言葉の選び方とタイミングの工夫で、誰もが快適に過ごせる空間をつくりましょう。
タメ口や命令口調を避けるには
見知らぬ人との距離感が重要な長距離バスでは、口調に気をつけることが非常に大切です。特に、タメ口や命令口調は相手を不快にさせる原因になりがちです。「そこ、ちょっとどいて」や「おい、出して」などの言い方は、たとえ悪気がなくても誤解されやすいです。
代わりに使えるのが、「〜してもよろしいでしょうか?」や「〜していただけますか?」といった丁寧な依頼表現です。たとえば、「通らせていただいてもよろしいでしょうか?」や「すみません、通していただけますか?」などが自然で印象も良いです。
また、「〜してもらえる?」のようなカジュアルな敬語も、状況によっては無礼に感じられることがあります。なるべく丁寧語を選びましょう。
気持ちの良い言葉づかいは、その場限りの関係でもお互いに気持ちよく過ごすための鍵になります。言葉一つで人間関係は大きく変わります。
年配の方や子連れの場合のひと工夫
長距離バスには年配の方や小さなお子さん連れの方も多く利用しています。こうした人たちに対しては、より配慮のある声かけが求められます。例えば、足元がおぼつかない高齢者に対しては、「ゆっくりで大丈夫ですよ」と一言添えると、安心感を与えることができます。
また、子どもを抱いたまま立ち上がろうとしている親御さんには、「お手伝いしましょうか?」と声をかけるのも親切です。もちろん、相手が恐縮しないような柔らかい口調を心がけましょう。
特に混雑しているバスでは、こうした一言が周囲とのトラブルを防ぐだけでなく、自分自身も気持ちよく過ごせる要因になります。
相手の状況に合わせた柔軟な対応ができる人は、自然と好印象を持たれやすくなります。誰にでも優しい言葉がけができるよう心がけましょう。
深夜バスでの小声・マナー対応
深夜バスでは多くの乗客が眠っており、わずかな音でも気になってしまう繊細な空間です。そんな中で声をかける必要があるときは、できるだけ小声で、相手の耳元に近づくのではなく距離を保って話すようにします。
例えば、「おやすみのところすみません、通りますね」といった小さな声でのひとことや、軽く手を振って気配を伝えるといった工夫が有効です。どうしても声が届かないときは、明るいスマホの画面を使わず、ライトをつけずに、相手が自然に目を覚ますのを待つのも一つの方法です。
また、話し声だけでなく、荷物の音、靴の音、シートベルトの金具音などにも注意しましょう。音を立てない工夫も、マナーの一環です。
静かな空間を保つために、自分の行動すべてに気を配ることが、深夜バスでの理想的なマナーといえるでしょう。
声をかけるベストなタイミングとやり方
出発前に声をかけるべき?
長距離バスに乗る際、「通路側の人に、あらかじめひと声かけた方がいいのか?」と悩む人もいるかもしれません。たしかに、窓側に座る人がトイレに行きやすいように、出発前に「途中で席を立つかもしれません」と伝えるのは親切です。しかし、状況によっては無理に声をかけない方が自然な場合もあります。
たとえば、相手がイヤホンをしている、眠そうにしている、スマホを見ているといった場合には、無理に話しかけるのは避けた方がいいでしょう。逆に、隣の人と目が合って軽く会釈を交わすなど、非言語的なコミュニケーションで「よろしくお願いします」の気持ちを伝えるのも一つの方法です。
声をかけるかどうかは相手の様子を見て判断し、無理に距離を縮める必要はありません。出発前に挨拶ができた場合は、「途中で席を立つかもしれません、よろしくお願いします」とひと言伝えておくと、お互いに気持ちよく旅を始められます。
無理に話すよりも、自然なタイミングで伝える「空気を読む力」が大切です。
寝ている人にはどうする?
長距離バスでは、隣の人がすでに寝ているという場面もよくあります。そんなとき、どうしてもトイレに行きたい、荷物を取りたいなどの理由で声をかけなければならない場合、相手を無理に起こすのは避けたいものです。
まず、軽く体を揺らすような動作や、少し距離をとった位置から「すみません」と小声で呼びかけるのが基本です。肩をトントンと叩くような行動は、突然すぎると相手が驚いてしまうため、できれば視線や声で反応をうかがいましょう。
起こしてしまったあとは、「おやすみのところ申し訳ありません」と一言添えると印象がよくなります。また、無言で立ち上がって相手の足元をまたぐなどの行為は、非常に不快に感じられることが多いため避けましょう。
寝ている人への配慮は、バス内のマナーの中でも特に重要です。「どう声をかけたら相手が安心するか」を想像しながら行動するようにしましょう。
言いにくいときの工夫
「声をかけたいけど、ちょっと勇気が出ない……」そんな場面もありますよね。特に内向的な性格の人や、人と話すのが苦手な人にとっては、たった一言の「すみません」さえハードルが高く感じられることもあります。
そんなときには、まず視線を使ったコミュニケーションを心がけましょう。隣の人と目が合ったら、軽くうなずいて意図を伝える。言葉で伝えにくいときには、身振り手振りで「通りますよ」と表現することもできます。
また、ボソッとした一言でも丁寧な印象を与えるコツは、「語尾に敬意を込めること」です。たとえば、「ごめんなさい、ちょっとだけ…」といった曖昧な言い方でも、相手に不快感を与えません。
どうしても難しい場合は、車内の係員に助けを求めるのも一つの手です。無理に自分だけで抱え込まず、周囲のサポートも活用しましょう。
荷物があるときの伝え方
荷物の出し入れや頭上の棚からカバンを取るとき、どうしても隣の人のスペースに干渉してしまう場面があります。そんなときは、事前に「すみません、荷物を取らせていただいてもよろしいですか?」と一言声をかけるだけで、印象が大きく変わります。
特に、通路側に座っている人は、窓側の人の荷物の出し入れに何度も対応することがあるため、声かけの有無が不快かどうかの分かれ目になります。また、荷物が重い場合や大きい場合には「少し時間がかかるかもしれません」と伝えると、相手も心の準備ができます。
このように、動作の前に一言を添えることが、スマートなマナーとして非常に大切です。自分の都合だけで動かず、周囲に配慮する姿勢を忘れないようにしましょう。
どうしても声をかけにくい相手への対応法
中には、隣に座っている人が無愛想だったり、強面だったり、声をかけにくい雰囲気の人もいます。そういったとき、無理に明るく話しかける必要はありませんが、無言で動くのも避けたいところです。
まずは、できるだけ自然な距離感を保ちながら、「すみません」と短く小声で伝えてみましょう。目を見ずに視線を少し下にすることで、相手に威圧感を与えずにすみます。
それでも反応がなかったり、あまりに声をかけづらい雰囲気なら、一度深呼吸してタイミングを見計らいましょう。目が合ったときに軽く手を上げて合図するなど、非言語のコミュニケーションをうまく使うのがコツです。
どんな相手であっても、敬意を持って接することがマナーの基本です。声のトーン、表情、動作のすべてで「敵意はありません」という雰囲気を伝えると、きっと相手も応じてくれるはずです。
座席マナーを守ることで旅全体が快適になる理由
トラブル回避に繋がる
長距離バスは、他人と近い距離で何時間も過ごす特殊な空間です。そのため、些細なマナー違反が大きなトラブルに発展することがあります。たとえば、無言で通路を塞いでしまった、リクライニングを断りなく倒してしまった、などの小さなことが積もり、乗客同士の口論やクレームに繋がることもあるのです。
実際に、バス会社によると「座席のリクライニングに関する苦情」は最も多いトラブルの一つとされています。こうしたトラブルはバス内の空気を悪くするだけでなく、乗務員や他の乗客にまで迷惑をかける可能性があります。
その点、マナーを守ることでトラブルの芽を事前に摘むことができます。一言声をかける、周囲に気を配る、それだけで余計なストレスや摩擦を避けることができるのです。
安心・安全な旅のためには、自分の行動が他人にどう影響するかを常に意識することが大切です。マナーは「自分を守る手段」でもあるのです。
相手の印象をよくする効果
座席マナーを守っている人には、「この人、感じがいいな」「一緒にいてストレスがないな」といった好印象が自然と生まれます。特に、通路側という“動線の要”にいる場合、ちょっとした一言や動作の丁寧さで印象がガラリと変わるのです。
たとえば、「通りますね」「すみません」といった声かけが自然にできる人は、それだけで“人としてしっかりしている”という印象を与えます。逆に、無言でどかれたり、足を通路に出したまま動かなかったりすると、不快感を持たれることがあります。
旅は「人と人との一時的な共有空間」です。その中で、たった数秒のやりとりが相手の記憶に残ることもあります。だからこそ、どんな場面でも礼儀や配慮を忘れない人は、どこへ行っても信頼されやすくなるのです。
見えないところで評価される、そんな“気遣い力”が座席マナーには詰まっています。
眠りやすさ・リラックス感が増す
マナーが守られている空間では、自然と緊張がほぐれ、リラックスしやすくなります。とくに長時間の移動では「心地よい空気感」が大きな影響を与えます。無言でリクライニングを倒されたり、隣の人が足を広げていたりすると、眠りづらくなり、体にも心にも負担がかかります。
逆に、適切な声かけや控えめな振る舞いがあれば、安心して身を預けることができるため、睡眠の質も向上します。特に夜行バスでは「少しの不快感が眠れない原因になる」ため、マナーを守ることは自分にとっても大きなメリットです。
マナーのある人が隣にいるだけで「この人なら安心」と思え、無意識に身体がリラックスするというのは、実際に乗車した人がよく口にする感想です。
心地よい空間をつくる第一歩は、自分自身がマナーを守ることから始まります。
運転手や他の乗客への影響
座席マナーを守ることは、隣の人だけでなく、運転手や他のすべての乗客にも良い影響を与えます。たとえば、通路をふさがずスムーズな乗降ができることで、バスの遅延を防ぐことができますし、静かに話すことで車内の騒音も減ります。
運転手は、車内の状況をミラーなどで常に確認しています。乗客同士がトラブルを起こしていれば、その対応に気を取られ、運転に集中できなくなることもあります。つまり、乗客のマナーが運転の安全性にまで影響するのです。
また、他の乗客にとっても、マナーを守っている人が多いほど「このバスは快適だ」と感じられ、全体の空気が良くなります。逆に、一部の人がマナーを守らないと、周囲に悪い影響が広がりやすいのも事実です。
良い空気感は、良いマナーの積み重ねでつくられます。全体の快適さを考えた行動が求められます。
リピーターとして気持ちよく旅を終えるために
快適な旅の締めくくりは「気持ちよくバスを降りられるか」にかかっています。どんなにサービスがよくても、隣の人との気まずい空気やマナー違反のストレスが残っていれば、その旅の印象は大きく下がります。
逆に、お互いに気を配り合い、トラブルなく終えられた旅は、また同じ交通手段を選びたくなるものです。とくに長距離バスを何度も利用する人にとって、「居心地の良さ」は非常に大きな判断材料です。
また、バス会社にとっても「マナーの良い乗客」が多い路線や便は管理がしやすく、質の高いサービスが維持されやすくなります。結果として、より快適な設備やサービスが提供されるようになるという好循環が生まれます。
つまり、マナーを守ることは、未来の自分にとってもプラスになるのです。「また利用したい」と思えるような旅にするために、マナーの意識を持ちましょう。